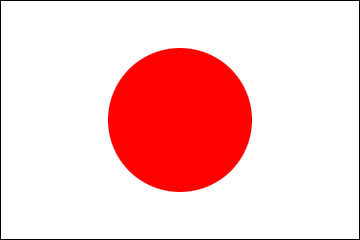過去のお知らせ(2003)
海外渡航情報(SARS広域情報)の発出 重症急性呼吸器症候群(SARS)患者の発生
※ 本件渡航情報は下記の通り発出されましたが、随時更新されます。
| 1. | 今冬になって最初のSARS患者が台湾において発生しました。 | ||||||||
|
|||||||||
| 2. | 重症急性呼吸器症候群(SARS)については、今年7月5日にWHO(世界保健機関)がSARS終息宣言を出しましたが、その後、9月にシンガポールの研究所で男性大学院生が感染したケースが発生しました。今回の台湾のケースについても、患者の隔離など適切な措置がとられておりますが、今冬に向けてSARSがいつどこで再び流行するか予断を許さないところです。 | ||||||||
| 3. | また、主にアジアの各国はSARS対策の観点から、出入国時の検疫措置をとっており(各国における出入国時の措置については、外務省海外安全ホームページ「重症急性呼吸器症候群(SARS)関連情報」の「4.その他のSARS関連情報(1)SARS基礎情報(ハ)各国における出入国措置」(アドレス:http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/sars/index.html)をご覧下さい。)、場合によっては微熱等であってもSARS感染を疑われ、これらの国からの出国ができなくなる可能性もあります。 | ||||||||
| 4. | ついては、海外渡航または海外滞在に際しては、改めて健康状態に十分注意するとともに、予防対策をとるなど下記の事項に十分留意して行動し、常に関連情報の入手に努めるようにして下さい。 | ||||||||
|
重症急性呼吸器症候群(SARS)講演会の概要
日時 2003年(平成15年)11月24日(月) 第1回目 15:00-16:30頃 第2回目 19:00-20:30頃 場所 香港コンベンション・アンド・エキシビジション・センター 301B 講演者 国立感染症研究所感染症情報センター長 岡部信彦氏
講演要旨 1. SARSの基本となる知見 ・主な感染経路は、極めて近い距離での直接感染と飛沫感染である。 ・症状のない人からの感染は、極めて少ないかゼロ。 ・重症者からの空気感染の可能性は現在のところ否定できない。 ・感染力は低いが、罹った場合の死亡率は10%程度。 ・感染力は、例外(スーパースプレッダー)を除けば、それほど強いものではない。 ・感染地域からの郵便物、輸入品からの感染の報告はない。 ・過剰な警戒は不要である。
2. 予防方法 ・手を洗う事が最大の予防方法であるが、洗うだけでなく、適切にふき取る事で初めて予防効果がある。 ・マスクは、飛沫感染を避けるために使用するのであれば、外科用マスクで十分である。 ・うがいは良い習慣である。 ・消毒方法は、熱湯、アイロン、紫外線、医療用アルコール(80%)、漂白剤、中和洗剤、界面活性剤、ヨード剤等が上げられるが、拭くこと及び浸けることが重要である。
3. SARS対策と感染症対策 ・SARSの感染を防ぐための対策は、他の感染症の予防にもなる。 ・手洗いをきちんと行うこと及び日常の健康管理を行う事が重要である。 ・また、有症者やSARS患者と接触した者が、無理に働かないですむ環境作りが大切である。
4. 今冬の流行の可能性 ・SARSが発生してから1年経っていない現状では、はっきりした事はわからない。 ・ただし、SARSの理解が進んできているので、感染の拡大は防ぐ事ができよう。
講演概要 <国立感染症研究所感染症情報センターの活動について> 国立感染症研究所感染症情報センターはSARSに限らず、感染症の動きを調査し、今後の対策を考えることをしている。SARSについて言えば、本年の2月くらいから不明肺炎と言うことで行動を開始していた。SARS流行時には、感染症研究所から、WHOの一員として、ベトナム、香港、マニラに人を送り、調査を行った。香港では、プリンス・オブ・ウエールズ病院、メトロポールホテル、アモイガーデンに人を送って調査した。
<感染症とは何か> 1.感染症と伝染病 (1) 感染症とはどういうものかを理解することが、SARSの対策に結びつくと言うことで、まず、感染症について説明したい。かつては伝染病と呼ばれたが、最近は主に感染症と言う。人にうつってくるもの全てを「感染症」と捉えており、かつての人から人にうつると言う意味合いの強い「伝染病」より広い意味があるが、実際は同じ意味である。 (2) 「感染する」ことと「感染症になる」のは別のことである。微生物が体内に入って「感染する」が、体内で微生物が増えても症状が出ないことや、そのまま人間と共生して条件が悪くなると症状が出てくることや、急速に肺・肝臓・喉が悪くなることもある。症状が出てくると「感染症になる」と言い、微生物が増えてくる過程は「潜伏期」である。
2.最近の感染症の動向 (1) 1996年に大阪で発生したO157では約9,000人が感染し、最近香港でも流行った手足口病ではマレーシアで30人、台湾で50人が死亡している。 (2) 1997年に香港で発生したトリ型インフルエンザ(H5N1)は、初めて動物(鳥)から人にうつったものであった。18名感染して6名死亡したが、人から人への感染はないとされた。新型インフルエンザかも知れず、その場合には感染者数や死亡者数が高くなる可能性も危惧されたが、その後は人への感染がなかった。 (3) 2003年2月に香港から中国福建省に行った家族がトリ型インフルエンザ(H5N1)感染し、死亡者が出たため、流行が危惧された。
<SARSの発生とその経過> 3.肺炎とSARS (1) 肺炎は昔からあり、感染症が原因であることが多く、症状も発熱・咳・息苦しさ・肺が白くなる、と共通している。途上国を含めた肺炎の死亡率は、WHOによれば、感染症の中で世界第1位である。日本でも、肺炎は、1950年には死亡原因の第3位、2001年でも癌・脳卒中・心筋梗塞に続く第4位であるが、以前と比較すると、基礎疾患や慢性の病気と肺炎が組み合わさって死亡することが多く、肺炎単独の死亡事例は減った。 (2) 新聞などでは謎の肺炎とされたが、肺炎自体は珍しくない。肺炎は、肺の組織が壊れて(従って息苦しくなる)レントゲン写真で白くなることで判明するが、何が肺炎の原因かはレントゲン写真では分からないので、他の症状等を含めて見ていき、既知の肺炎と異なったものがSARSであり、重症化して急性に進行するものであった。病原体については、4月半ばに、香港の尽力もあって、新種のコロナウイルスと判明した。 (3) 日本では、当初SARSは、感染症法上の「新感染症」に分類され、ウイルスが判明した段階で「指定感染症」となり、改正感染症法により「一類感染症」となった。このことにより、医療機関で行う隔離・搬送・費用について法律に基づく行政的対応を取ることができることになった。
4.各国のSARS発生状況と日本の疑い例・可能性例 (1) 世界中の本年2月から4月までのSARS流行曲線を見ると、香港・中国等は山型の流行で、ベトナムは早く終結し、米国や欧州では櫛の歯が抜けたような必ずしも流行の山がはっきりしないパターンを見せた。この流行曲線の違いは、米国・欧州では、域内で人から人への感染がなかった、また、台湾・香港・中国・シンガポール・カナダ・ベトナムでは、域内で人から人への感染が生じたためである。 (2) 日本では、疑い例が52例、可能性例が16例あったが、国内SARS対策専門家委員会で、いずれもSARS以外の病気で説明できたため、WHOへの報告はゼロであった。 (3) 日本の疑い例・可能性例の68例(全てSARSではなかった)を見ると、東京が多いが、旅行者人口比で捉えると、どこも大体変わらない。日本人は、日本国内各地から旅行に出かけているため、診察側は、日本中どこにでもSARSはあり得ると言うことを考えなければならない。
5.SARS流行の過程 (1) 後で取りまとめてみると、中国で2002年11月から原因不明の肺炎が流行しており、患者を治療していた中国の医師が香港に来て発症し、ホテルの宿泊者に感染させ、ここから、ベトナム・カナダ・アイルランド・米国・シンガポール経由でドイツ・バンコクへと感染が拡大した。仮に空気感染であればエアコンを通じるなどにより、別のフロアでも感染したはずであるが、感染者は、ホテルの同一フロア宿泊者に限られていた。従業員には感染しなかった。 (2) SARS患者が入院していたプリンス・オブ・ウェールズ病院の8A病棟は、大部屋で仕切りがないが、感染したのは比較的近いベッドにいた患者であり、離れるに従ってほとんど感染していない。また、ブロックに立ち入って実習した、医学部の臨床実習生も感染した。 (3) 香港やベトナムでは当初院内感染だけと思われたのが、香港では社会に拡がった。アモイガーデンでは1万数千人の住民のうち約300名が感染した。SARSの患者は下痢をし(下痢にウイルスが含まれることが後に分かった)、WHO及び香港も、調査からアモイガーデンでは下水の排水不備により逆流しやすかったことから、感染の原因となったのではと分析した。また換気扇によって部屋全体が陰圧となりウイルス粒子を引き込み易くなっていたことも原因となったと思われる。しかし、アモイガーデンを除けば、香港のみでなく、台湾でも北京でも、一般市民居住区での感染はあまりなく、ホテルでの感染も次々に起こることはなかった。 (4) WHOの調査では、航空機内での感染27例のうち22例が特定の航空機1機の事例であった。症状の出ている人が搭乗すると感染の可能性があるが発症前の人からの感染例はない。症状のある人は、航空機に乗らないか、他の人と別にすることが必要である。人は、自分が感染するかもしれないことに対しては敏感だが、自分が他人に影響を与えると考える人は必ずしも多くはないので、それぞれが改めて自覚する必要がある。
6.SARSの臨床経過と感染 (1) SARSコロナウイルスの潜伏期間は、平均5-6日、最大10日である。潜伏期間を経過すると、急激に発熱し、次いで乾いた咳が出て、痰が出にくい、息苦しいといった症状が現れる。80%から90%の人は回復するが、10%から20%の人は重症化し、人工呼吸装置の装着などが必要となる。SARSの全世界の致死率約10%と比較すると、例えば、日本での結核の致死率は8%位(毎年2,000人から3,000人が死亡)であり、ほぼ同程度である。 (2) SARSは、潜伏期間に感染するという報告はない。WHOは、潜伏期(発症前)の感染は、なし又は非常に低い(zero or very rare)と言っている。症状が出てくると少し感染力が出てくるので、警戒が必要である。肺炎をおこす、呼吸困難、咳等が出てくると急激に感染力が上がってくるので(平均2-3人に感染)、医療関係者は相当厳重に注意する必要がある。 (3) 感染症全館の感染方法は、接触感染(血液・痰・便・尿・膿・体液)、飛沫感染(唾の水分に微生物が含まれる、せいぜい1mだが、安全を見て1mから2m)、空気感染(数m、風に乗ったりエアコンに吸い込まれたりする)、媒介物感染がある。感染症の多くは接触感染か飛沫感染であり、空気感染するのは、はしか、水ぼうそう、結核、ペスト。
<SARSを予防するためには> 7.標準予防策 (1) 院内感染を避けるためには、標準予防策が重要である。素手で触ったら、石鹸で手を洗うこと。できれば手袋があれば良いが、手袋をつけたとしても外したら手を洗うこと。手袋・エプロン・マスク・ゴーグルは使える状態にしておくこと。病院ではバリアナーシング(宇宙服的なもの)もあるが、いきなり最先端のものというのでなく、まず最低限の標準予防策が重要である。 (2) 学校で手袋が必要かについては、通常は必要ないが、例えば、学校で出血やブツブツに触ることもあるので、その場合には手袋で触った後に手を洗うことが肝心である。 (3) 普通のマスクで、飛沫(5ミクロン)はある程度防げる。SARSのように飛沫感染するような所にいる人の感染を防ぐためには外科手術用マスクが適している。空気感染をも考えられる重症の人を診るのであればN95マスクであるが、N95マスクはきちんと隙間がないように付けなければ意味がない。また、N95マスクは、一般の人でも階段を上ると息苦しくなり、病人で息苦しい人は尚更なので、普通の人がこれを付けて(対策を)やったような気になるのはかえって危ない。 (4) うがいは、喉の粘膜を滑らかにする。うがいをすれば殺菌又はウイルスを殺す効果がある。効果は持続的なものではないが、きれいにする意味ではうがいをした方がしないよりは良い。日本と韓国の一部で行われているうがいは、折角良い習慣だから止める必要はない。 (5) 手を洗うのは感染予防の最大の武器だが、指の間も良く洗い、きちんと乾かす、きれいに拭き取ること。アルコール系消毒剤を付けても、きちんと乾かすことが必要。濡らした手をハンカチで拭いてまた同じハンカチを使っては意味がなく、正確に行って初めて効果がある。石けんが無くとも、水道水だけでも良いので、石けんを使うのと同じくらいの時間をかければ、同じ効果があるというデータもある。
8.SARSの感染経路 (1) SARSは、接触感染と飛沫感染(1mから2m程度の濃厚接触)が中心。アモイガーデン及びメトロポールホテルの感染例並びに重症患者では、空気感染を全く否定はできないが、WHOでは空気感染を証明する報告はない(no evidence)としている。動物や住宅からの感染は否定できないが、中心ではない。従って、接触感染及び飛沫感染に最大限注意し、感染力の強い所(医療機関内等)では空気感染なども注意することになる。 (2) 感染力は個人差があり、SARSでは1人の患者から2、3人(はしかは15人、インフルエンザは10人近い)とそれほど高くないが、スーパースプレッダーがいる。その多くは極めて重症の患者であり、ほとんどの人が亡くなっている。症状の軽い人の感染力は高くないが、注意は必要である。 シンガポールの例では、患者の81%は他人にまったく感染させていない一方、1人の患者が12人・21人・23人といった多くの人に感染させた例いくつかがあったが、これは当初病院内で防護を十分に行わなかったためであった。
9.消毒 消毒方法は、熱湯、アイロン、紫外線、医療用アルコール(80%)、次亜塩素酸ソーダ(漂白剤、最近0.05%ではちょっと効かないのではないかという話も出てきているが)、中和洗剤、界面活性剤、ヨード剤などがある。 噴霧器は、先に噴霧するとウイルスを吹き飛ばしてしまう可能性があるのできちんと拭くことが肝心。噴霧器は、届きにくい所まで届くと言う効果はあるが、噴霧によってウイルスが死ぬのではない(空気中にウイルスがいるのではないため)。
<SARSについて現在判明していること> 10.SARSの基本となる知見 ・主な感染経路は、極めて近い距離での直接接触と飛沫感染(1m―2m位)。 ・空気感染の可能性は否定できないので、重症の人を扱う所では空気感染を含めた対策をしておいた方が良い。 ・症状のない人からの感染の可能性は、ゼロ又は極めて少ない。 ・市中での感染の可能性は、ゼロではないが、極めて低い。 ・感染地からの輸入品・郵便物は心配ない。過剰警戒は不要。 ・感染拡大の中心は医療機関。 ・感染力はインフルエンザより低いが、かかった場合に約10%の致死率がある。
11.今冬の再流行の可能性 はなかぜのコロナウイルスは冬に流行する、前回のSARS流行は冬にスタートした、気温が低いとウイルスが拡がりやすい、前回の流行も対策が功を奏したのではなくて結局暖かくなったので消えただけ等という見方があるが、1年足らずの流行でははっきりしていない。今冬に再流行するかどうは誰にも分からないが、南半球ではすでにインフルエンザの流行期間は収まりつつあるのに、SARSは発生していない。いずれにしても、理解が進んできているので、大規模な感染の拡大は努力によって防ぐことができるであろう。本年9月のシンガポールの感染例に見られるように、日本で今後1- 2例くらい出たとしても、冷静に対応することが大切である。
12.インフルエンザとSARS (1) 2003年のインフルエンザの中規模流行の年(大流行と言われたが、過去10年間で4番目)に、感染症研究所が全国5,000か所からの報告をまとめたところ、約120万人のインフルエンザ患者がいた。これから推定すると、同年の日本全国のインフルエンザ患者数は約1,500万人になる。 (2) インフルエンザとSARSを比較すると、潜伏期間は、インフルエンザは1日-3日、SARSは2日―10日。潜伏期間での感染は、インフルエンザは低く、SARSはゼロ又はほぼない。発病した場合の感染力は、インフルエンザは非常に高くなり、SARSは熱の出始めた時にはまだ高くないので、少し様子を見て早めに病院に行って欲しい。発病後1日―2日すると、インフルエンザは症状が下がるが、SARSは上がっていき、肺炎の状況を呈すると感染力も増大する。従って、SARSは、肺炎のタイミングを見逃さなければそれほど周りに拡がりがなく、肺炎と分かったら医療上防護することが極めて重要になる。
13.SARS対策と感染症対策 (1) 感染症を全て根絶することは困難であるが、少しでも感染者の基本的な対応を取ることにより全体の感染数を減らすことができる。SARS対策を行うことは、全体の感染症の対策にもなり、その逆も然りである。学校や企業では、手洗いをきちんとし、マスクを用意しておくこと。日常の健康管理も重要である(例えば、結核の健康診断を受けていない人も多い)。SARSの致死率の面でも、糖尿病や血圧の高い人など基礎疾患のある人は重症化しやすい。 (2) 予防接種で防げる感染症であれば予防接種を受けておいた方が良い。予防接種は決して子供だけのものではない。 (3) 仕事面でも、有症者・接触者が無理に働かないで済む環境が重要である。海外では、病状に応じて受診すべき医療機関を予め調べておくことも必要。SARSは極めて問題となったことは事実だが、実は他の感染症でそれより多くの被害が起きている。
<終わりに> 国立感染症研究所感染症情報センターでは、必ずしも一般向けではないが、今年のSARS対策、WHO情報の翻訳などが掲載されている。 アドレスは、http://idsc.nih.go.jp/index-j.html。
質疑応答 <第1回目講演より> (問)香港で、治った患者の中で、薬によるかなり重い後遺症が出たと報道されているが、副作用の少ない治療薬があるのか。また、消毒薬は80%濃度のものが良いとのことだが、薬局では75%濃度のものが多いが、大丈夫か。 (答)治療方法として確立されているものはない。香港ではリバビリンは効果があるとしている一方、米国の研究所は否定しており、論争中であるなど、これが確実に良いという治療方法はない。日本でリバビリンが認可されていないのは、(C型肝炎には使われているが)治療用としては副作用が重いためである。評価が固まっていないのに緊急輸入して使う段階になっていない。香港では医者の経験からリバビリンとステロイドを使用したが、それぞれの機関が良いと考える方法で治療している。 消毒用アルコールは、本当は80%が良いが75%でも使用出来る。良く手に入る「こするタイプ」の物も良い。また、たとえ家庭用で80%のものを使用していても、ふたの開閉によっては濃度はかなり下がってしまうので、きちんとふたを閉めることが必要である。1つ1つパッケージになっているアルコール綿なども使いやすい。
(問)香港及び世界で報告されている後遺症の状況を聞きたい。 (答)あまり情報が入ってきていない。ほとんどの患者は回復しているが、病気そのものにより呼吸困難や続いていたり、肺機能が弱くなっていたりというのがある。これが、病気が原因なのか薬が原因なのかはまだ明らかになっていない。少なくとも、慢性の状態になって再度病気になる状況にはない。ほとんどの人は回復しており、極めて少数の人に呼吸障害があるが、どのくらいの人がそうなのかは報告が届いていない。
(問)インフルエンザの予防接種が実はあまり効果がないとサイトや雑誌で見たことがあるが、どうか。 (答)ワクチンをどう捉えるかによる。例えば、ポリオはかつて日本で5,000人から6,000人の患者がいたのが、ワクチン導入により患者が激減し、ここ20数年間患者がいない。一方、水ぼうそうは、ワクチンの効果が完全なのは80%位の人で、20%の人は軽い水ぼうそうになり得る。インフルエンザのワクチンは、年齢にもよるが、お年寄り場合の70%は入院しない・高熱がでなくて済む・死亡しないという効果があるが、残りは予防接種したにもかかわらず重症化するものがある。ポリオと比較すると効果は少ないが、予防接種によって確実に患者数も死亡者数も減少するので、3分の2位に効果があることを受け入れるかどうかということになる。今の日本の考え方は、高齢者の3分の2に効果があり、高齢者が亡くなる確率が少なくなるなら、薦めるべきということになる。効果があると言うことは、他の年齢でも当てはまる。ただし、小さい子供では最近50%位というデータも出てきているが。
(問)香港におけるSARSの最終的な医学的な確定方法を聞きたい。 (答)世界的にも確定する方法はない。一番確実なのは、病気になった時と治った時の血液(3週間から4週間の間隔が必要)を採り、血液中の免疫が上がってくることをみる方法があるが、急性期の確定ができない。このため、急性期には遺伝子によるPCR法やウイルス分離法が採られているが、確定的な方法はない。日本で開発されたと報道されている迅速診断法(LAMP法)は、PCR法より早くて安いが、現在は患者がいないため、実際の検体を使って実験できていない。認可するかどうかは議論中である。
<第2回目講演より> (問)SARSで10%、トリ型インフルエンザで30%の致死率となっているが、SARS及びトリ型インフルエンザの致死率において、不顕性感染(症状が表れない感染)をどのように考慮しているのか。 (答)致死率を出す場合、発症者だけを対象にする場合と症状が出ない人も合わせて対象にする場合がある。SARSの場合は、現在は、国によっても異なるし、全部が確定診断できていない状況であるので、定義としては、少なくとも肺炎を起こした可能性例を分母とした死亡者と言う致死率である。 トリ型インフルエンザの死亡率の場合は、発症者分の死亡者である。なお、トリ型インフルエンザは、不顕性感染はなかった。
(問)全員がマスクをするべきなのだろうか。 (答)SARSの場合、誰が感染しやすいのかを考えると症状の出た人から感染しやすい。症状の出ている人がマスクをすれば、他の人が感染しにくい。また、症状の出ている人を診る医療関係者もマスクをした方が安全である、しかし、症状が出ていない人の集団の中でマスクをすることは、あまり科学的な意味はないし、まして強制をするものではないと思う。ただし、不安を感じる人も中にはいるので、そのような人たちに安心感を与えると言う意味で個人的防衛としては良い意味になるのではないかと思う。
(問)SARSの期間中、多少体調が悪くても、病院に行かない人が多かった。病院(クリニック)での受診を避けるような状況だったが、そこまでする必要があったのだろうか。 (答)最初の頃は不明な点が多く、止むを得なかったかもしれないが、健康診断は必要である。医療機関の時間的な選別と、受診者のアポイントの取り方で状況が違ってくるのではないか。自分は、もともと小児科であるが、健康な赤ちゃんに病気をうつされては困るので、小児科の場合、健康診断と普通の受診時間は分けるのが原則である。このように、時間的な選別を行えば、病院における健康診断なども可能であると思う。
(問)今回のSARSの期間中に10日間の自宅隔離措置があり出張者が来られなくなったりしたが、現在SARSについて判っている事から言えば、同じような事が起こった場合でも自宅隔離措置などは行わなくてもよいのだろうか。 (答)国立感染症研究所のホームページにも掲載されているが、症状のない人に生活上の制約を加えることは、必要のない事であると言える。ただし、感染の可能性があると考えられる人は、熱を測る、体調が悪ければ受診する等をきちんと行ってほしい。 学校について言えば、子供への影響が判っていなかった時点では、10日間の自宅隔離は止むを得なかったのではないかと思う。 ただし、成人の場合は、自己管理ができるので、自分としては10日間の自宅隔離は実際的ではないと思う。
重症急性呼吸器症候群(SARS)の再流行対策
SARS再流行対策について、日本総領事館からの要請に対し、9月9日、香港政府より概要次のような回答がありました。なお、香港政府の対策の詳細は、http://www.info.gov.hk/gia/general/200308/26/0826225.htmでご覧頂けます。
1. 新規ケースの輸出入防止 体温検査と健康状態申告書の提出を継続。 2. 感染予防対策(インフルエンザ・ワクチン接種) 香港の一般市民には、インフルエンザ・ワクチン接種を推奨(約100香港ドルの接種料金は自己負担。なお、市中の病院では、この他に数百ドルの初診料を併せて請求されることが通例)。老人ホーム入居者、危険性の高い入院患者、ヘルス・ケア・ワーカーに対しては、無料で接種。 3. 病気監視のための広東・香港・マカオ間の協力体制 広東・香港・マカオ間で、SARSは毎週1回、SARS以外の約30種類の感染症は毎月1回、相互に感染者数と疑い者数とを通報。SARS流行時には即日通報。広東省はSARS感染者数が1名であっても公表する体制。香港においても広東省のSARS患者数を公表。 4. 公立病院の感染防止施設 既存の病院に感染症対応の隔離病棟・病室を設け、隔離ベッドを、1,300床弱に増設予定(本年11月までに予定数の約80%を満たす予定)。 5. シンガポールの感染例 シンガポールでの事例は、単独の感染例。一般社会から感染したものではない。 6. 臨床管理 PCR検査法は、迅速だが、確実ではなかったため、これを補う信頼性のあるSARS診断方法を開発中。 7. 高齢者対策 老人ホームに医師とヘルス・ケア・ワーカーが週1回から2回定期的に訪問する体制を、少なくともあと1年継続予定。 8. 研究開発 大学関係者や研究者等からSARS関連研究開発案件の申請を受付中(本年10月まで、予算4.5億香港ドル)。 9. 病気監視のためのデータベースの構築 「e-SARS」というデータベースで、公立病院と医院管理局・衛生署を結び情報を共有。今後は、SARS以外の感染症の情報も共有可能とする予定。 10. 感染症対応のスタッフ育成 医院管理局は5年計画で様々な訓練を計画。また、診療所・小規模病院等の私立病院と、公立病院・政府機関とが密接に連携。 11. 緊急措置 香港全体・地区・病院の各レベルでの緊急措置計画をSARSに対応して改善。 12. 再発防止・準備対策の一般社会への周知 8月26日に、SARS再発防止・準備対策を発表。また、9月8日、政府機構横断的な委員会を開催、再発防止・準備対策を具体化。
主要な追加改訂部分は青色・斜体になっています。
(SARSの日本語名は重症急性呼吸器症候群。メディアでは「非典型肺炎」という言葉がよく使われます)
予防策 (1)マスクの着用、(2)うがい手洗い、(3)人混みを避けるといった物理的手段のほか、規則正しい生活、十分な休息、栄養バランスに富んだ食事、たばこを控えること等によって全体的な抵抗力を高めることが効果的とされています。
感染した場合の自覚症状 38度以上の熱、悪寒、咳、下痢、息切れ、頭痛、筋肉のこわばり、全身の倦怠感等です。これらの自覚症状がある場合には、速やかに下記の病院等に連絡し検査を受けて下さい。
●香港政府のSARSホットライン 2961-8968 ●日本語で受診できる病院
下記の病院は、日本語の通訳がいる病院です。日本語での診察には予め予約が必要ですので、詳細は各病院にお問い合わせ下さい。
九龍 Baptist Hospital 電話:2339-8911、住所:222 Waterloo Rd. (九龍塘) 救急24時間、月~金:9:30~13:00、14:00~17:30、土:9:00~13:00
香港島 Adventist Hospital 電話:2835-0509 住所:40 Stubbs Rd. (湾仔) 日~金:9:00~12:30、14:00~17:30、土:休み、日本人スタッフ Sanatorium & Hospital 電話:2835-8600 住所:2-4 Village Rd. Happy Valley (ハッピーバレー) 救急24時間 24時間、日本語は月~金:9:00~17:00、土:9:00~13:00 St. Paul Hospital 電話:9030-6821 住所:2 Eastern Hospital Rd. Causeway Bay (銅鑼湾) 緊急24時間、外来24時間、日本語は月~土:8:00~20:00、日本人スタッフ Canossa Hospital 電話:2522-2117 住所:1 Old Peak Rd. (ミッドレベル) 緊急24時間 24時間 Matilda Hospital 電話:2849-1573 住所:41 Mt. Kellet Rd. (ピーク) 緊急24時間 月~金:8:15~17:30 土:8:15~13:00、日本人スタッフ
●最新情報が確認できる日本語のホーム・ページ 香港総領事館 https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 感染情報センター http://idsc.nih.go.jp/index-j.html
| ●SARSとは | ●コロナウイルス | ●検査法 |
| ●感染経路 | ●飛行機 | ●予防生活 |
| ●マスク | ●ただの風邪かもしれない・・・・・ | ●病院 |
| ●職場などにおける感染者の発生 | ●マンション | ●出産&子供 |
| ●出入境 | ●中国 | ●見通し |
| ●帰国 | ●日本および総領事館の対応 | ●WHO |
| ●その他 |
| 問 | 感染した場合の自覚症状はどのようなものですか。 |
| 答 | 38度以上の熱、悪寒、咳、下痢、息切れ、頭痛、筋肉のこわばり、全身の倦怠感等です。アモイ・ガーデンの集団発生ケースにおいては、特に下痢の症状がより普遍的に見られ、コロナウイルスの再変異の可能性を示すものとして注目されています。 |
| 問 | どのような場所で発生していますか。 |
| 答 | SARSの流行が始まった頃は、概して香港島よりも九龍サイドが多かったのですが、その後は香港、九竜、新界を問わず感染者が発見されました。また、衛生署はホーム・ページ上(http://www.info.gov.hk/dh/ap.htm)で過去10日以内に新たな感染者が発見されたマンションの名前と所在地を公開しています。 |
| 問 | 今年1月から2月にかけて、高熱、痰、咳を伴う風邪を家族でひきました。今はもう治っていますが、そのときSARSだったのでしょうか。 |
| 答 | その可能性はありません。仮にコロナウイルスに感染して発症しSARSの可能性が疑われたとしても、そのうち8~9割は3~5日で快復し、SARSとなるのは1~2割程度です。つまり、コロナウイルスに感染することイコールSARSではなく、SARSとは呼吸器系に異常が起こる症候群の総称であり、今回のSARSはその原因がコロナウイルスと考えられているのです。 |
| 問 | SARSから通院せずに快復する方法や可能性はありますか。 |
| 答 | 一旦SARSを発症した場合に通院せずに快復するのは現実的ではないと思われます。むしろコロナウイルスに感染してもSARSを発症することなく快復することの方が多いです。 |
| 問 | いま香港で流行しているSARSは昨年末に日本で流行したインフルエンザとは違う種類のものなのですか。 |
| 答 | いま香港で流行しているSARSとインフルエンザは全く別の疾患ですが、症候群としては似ています。しかし、インフルエンザの肺炎とコロナウイルスの引き起こす非定型肺炎(新型肺炎)は明らかに発生メカニズムが異なります。インフルエンザウイルスが直接細胞障害を引き起こすのに対しコロナウイルスは直接細胞障害を引き起こさず、過剰な免疫反応を導き、その結果白血球が自らの肺を攻撃することにより肺炎を起こします。 |
| 問 | 日本製のマスクは洗うことでフィルターの効果が半減していくと書かれていますが、使い捨てマスクのほうが良いのでしょうか? |
| 答 | マスクは目の細かいものが効果が高いと考えられます。近くに感染者がいない場合、使い捨てマスクで十分です。目の粗い布製マスクは余りおすすめできません。 |
| 問 | 会社の入っているビルで感染者が出たようなのですが。 |
| 答 | 事務所があるビルで感染者が出たとしても、当該ビルに対して隔離措置がとられなければ、事務所を閉める必要はないといえます。これは同じフロアーで感染者が出た場合も同様です。職員に感染者が出た場合、出勤させずにそのまま病院に向かわせることが必要です。それは、職場での感染を防ぐためです。万が一、職場で発症している職員を発見した場合には、他の人も感染の危険がありますので、直ちに衛生署に通報し(ホットライン2961-8968) 、消毒、隔離などの措置に協力してください。 |
| 問 | 社員の住んでいるマンションで感染者が出ました。その社員には健康上、何の変化もありませんが、どのように対応すべきでしょうか。 |
| 答 | (1)発症していなければ他人に感染させてしまう可能性は非常に低いと考えられ、かつ発症していない人から感染した実例は確認されてはいないので、それを前提に考えれば、その社員の方を出社させてもかまいません。職場で生じる心理的抵抗が懸念される場合には、社員にマスクを着用させることによって周囲に安心感を与えることができると思います。 (2)なお、参考までに香港衛生署のホーム・ページに掲載されている見解の要約を以下に引用いたします。 同じ建物の中で働いていても、発熱、咳、呼吸困難、下痢などの症状がある患者との密接な接触が無い限り、他者が感染する可能性は低いと言えます。ここに言う密接な接触とは、「患者を介護した」であるとか、「患者と同居している」であるとか、或いは「患者の唾液や体液に直接接触した」ことを指します。同じオフィスで働いている、或いは同じ建物の中にいることは密接な接触には含まれず、感染を過度に心配する必要はありません。衛生署は100倍に希釈した漂白剤による電話、スイッチ、応接室の机・椅子床などの消毒が予防措置として最も重要だと考えます。もし同じ建物で働いている人がSARSに感染した可能性があるか感染が確認された場合には、上記のような場所の徹底的な清掃と消毒が必要になります。患者と日常的な接触があるだけの同僚は通常と変わることなく働くことができます。清掃・消毒後は個人の感染防止に努めれば感染の可能性は非常に低いため、その他の職員を出勤させないことは公衆衛生の観点からは正当化できません。 |
| 問 | 社員の家族に課している移動の制限は解除しても良いでしょうか? |
| 答 | まず、個人における感染防御が基本です。感染の機会を減少させるために、人の移動を制限することは効果的です。今回のコロナウイルスより感染力の強い感染症であれば、政府、WHOは一層強い制限をすることでしょう。病気をうつさない、うつされない事が重要です。 |
| 問 | 香港に事務所を構える企業はSARSにどのように対応しているのでしょうか。何か情報はありませんか。 |
| 答 | 企業によっては、駐在員の中国本土への出張を制限したり、バックアップ・オフィスの設置、あるいは駐在員家族の一時帰国措置などの対応をとられていると聞いております。先日発表されたジェトロ香港実施の「香港に拠点をおく日系企業を対象に行ったSARSの影響に関するアンケート調査」も参考になると思います(http://www.jetro.org.hk/index.aspのSARS関連情報17・アンケート結果)。 |
| 問 | 香港国際空港での出入境に制限はありますか。羅湖駅やその他の場所での出入境に制限はありますか。 |
| 答 | 現在、香港空港では出入境に際し、以下の措置をとっています。 出境の際は体温検査、入境の際は健康申告書の提出及び体温検査、乗り換えの際は体温検査が義務づけられています。基本的には38度以上の熱がなく、SARSの症状がない限り、通常の出入境及び乗り換え手続きに進むことが許可されます。体温検査の結果38度以上の熱がある場合は、空港で健康診断を受けることになります。診断の結果SARSの疑いがあれば、飛行機に搭乗できなかったり、また、入境直後に指定の病院に搬送されたりします。詳細は、香港国際空港のホーム・ページ(http://www.hkairport.com)及び当館ホーム・ページ(香港空港での健康チェック)(https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/)をご参照ください。 また、鉄道ではKCRの羅湖駅や紅ハム(Hung Hom)駅、海上輸送ではチャイナ・フェリーターミナル(尖沙咀)及び香港マカオ・フェリーターミナル(上環)、陸路では沙頭角(Sha Tau Kok)、文錦渡(Man Kam To)、落馬洲(Lok Ma Chau)の出入境所において、体温検査、健康申告書の提出による健康チェックが実施されています。 |
香港の医療事情(退院後に感染させる可能性、退院の基準、典型的な症候が現れない患者) (福利衛生・食物局による情報)
在香港総領事館
香港の医療事情について日本総領事館から福利衛生・食物局に情報提供を要請していましたところ、5月14日、概要次のような回答がありましたので、ご紹介いたします。
| 1. | 患者数 |
| 毎日の記者会見や報道発表からも分かるとおり、日々のSARS増加数は減少傾向にある。 | |
| 過去10日間は日々の増加数が1桁になっており、過去3日間は日々の増加数の平均は5名となっている。 | |
| 5月13日現在、病院には374名のSARS患者がいる。300名が治療を受けており、74名が退院前の回復期にある。 | |
| 集中治療室(ICU)に入っている患者数は57名となり、これは、3週間前の4月23日の110名という数字と比較して、大幅に減少している。 | |
| 5月13日現在、人工呼吸器を付けているSARS患者は50名を下回っている。 | |
| 患者の減少傾向は、病院管理局管轄下のICUベット、隔離ベット、人工呼吸器具が十分であることを反映している。 |
| 2. | 退院後に感染させる可能性 |
| 退院後の人間の糞便からコロナウイルスが発見された点については、PCR検査を用いた予備実験データが示唆するところによれば、SARSの遺伝子物質(RNA)であるコロナウイルスが、21日を経過した後であっても人間の糞便から発見される可能性があるということである。 | |
| 「このことは、生きているウイルスが存在することを意味するのではなく、また、他人に感染させるに十分な量が存在するということも意味していない」と、WHOが2003年4月29日に指摘している。 | |
| ある種の一般の病気においても、回復期であってもバクテリアやウイルスが人間の糞便に存在し得るということが強調されなければならない。 | |
| このような状況において、患者に対して必要な予防策が講じられる限り、社会で大きな心配をすべきでない。 | |
| これまでのところ、我々は1,090名の患者を退院させており、退院後の患者を通じて感染したケースは1つもない。 |
| 3. | 退院の基準 |
| 退院の基準に関しては、人間の糞便にコロナウイルスが存在しないことを確認することは、要件となっていない。 | |
| 病院管理局が患者の退院に際して最も考慮する点は、患者の健康状態である。 | |
| 現在、病院管理局は、患者が病気からの回復期に入った後5日を経過しなければ患者は退院させるべきではないと勧告している。 | |
| 回復期は、WHOの基準に従って病院管理局が定義しており、症候・血液検査・胸部X線写真から判断して患者の状態が改善しているべきことと、明確にしている。 | |
| 患者は、退院後14日間は必要な予防策を講じるように、必ず忠告されている。 |
| 4. | 典型的な症候が現れない患者 |
| 発熱の症候を示さない患者は、数例、特に高齢者に見られるだけである。 | |
| このような状況の解明に当たっては、さらなる臨床研究が必要である。 | |
| しかしながら、感染防止の点で言うと、全ての医療関係者は、SARS患者やSARSと疑わしい患者を治療していない病棟・病室であっても、全ての病棟・病室において多大な注意を払っている。 |
香港の医療事情について(福利衛生・食物局による情報)
在香港総領事館
香港の医療事情について日本総領事館から福利衛生・食物局に情報提供を要請していましたところ、4月23日及び24日、概要次のような回答がありましたので、ご紹介いたします。
| 1. | ベッド数 |
| 病院管理局(注:香港の公立病院を管轄)は、約3,000のベットをSARS患者用に指定。 | |
| 4月23日現在、確認されたSARS患者は831名(うち、698名が治療中、133名が回復期)。 |
| 2. | 集中治療室(ICU)数 |
| 病院管理局は、救急病院で375、非救急病院で44のICUのベッドを保有。 | |
| 4月23日現在、110がSARS患者により使用され、約180がSARS以外の患者に使用されている。 | |
| 現在ICUを使用しているSARS以外の患者のうち幾らかの者は非ICU病棟で治療を受け始めているので、必要であれば、SARS患者のためにさらにICUのベッドを空けることが可能。最近の1日当たりSARSと確認された患者増加数の動向に鑑みると、病院管理局はICUサービスに対する需要は完全に満たされ得ると予想。 |
| 3. | 医師数及び看護婦数 | ||
| 現在SARSに関与している医師及び看護婦数は次のとおり。 | |||
| 医師 1,300名(病院管理局管轄の全医師の28%) | |||
| 看護婦 4,570名(病院管理局管轄の全看護婦の23%) | |||
|
| 4. | 人工呼吸器 |
| 病院管理局は797セットの人工呼吸器を利用可能なものとしている。 | |
| ICUにいる110名のSARS患者のうち、人工呼吸器を使用しているSARS患者は約100名のみ。したがって、利用可能な数は十分ある。 |
| 5. | 収容能力 |
| 病院管理局は、合計約20,000床の一般救急用ベッドを有している(8,000床の学校・工場等付属診療所のベッド等を含まない)。 | |
| 合計で4,500名の医師(うち、150名は現在ICUで働いており、追加で500名まで展開可能)、20,000名の看護婦(うち、1,500名がICUで働く準備があるか又は訓練中であり、1,100名は既に働いている)。 |
| 6. | その他 |
| SARS患者は病院管理局が管轄している14の救急病院で治療を受けている。 | |
| 病院管理局は状況を緊密に監視しており、どの病院も過重にならないように患者の収容先を管理している。 | |
| プリンセス・マーガレット病院の例をみると、現在のSARS患者の受入数は約340名(うち、38名がICU、23名が退院前の回復期)。これは、4月第1週と比較すると緩和された状況。 |
●本情報は、パンフレットとなっております。PDFファイルとしてダウンロード可能ですので、ここよりファイルを入手の上、印刷して活用下さい。
●既配布済の本リーフレットにおいて、以下の部分に訂正がありますので、ご留意願います。なお、下記の本文の記述「本文中(注)」は、訂正済みのものです。 項目:「どのような予防措置を講じたらよいのですか?」(家庭や職場を清潔にしておく)洗剤濃度 「誤」濃い目の洗剤(洗剤51:水49)→「正」濃い目の漂白剤(漂白剤1:水49)
【よく聞かれる質問】
「SARS(重症急性呼吸器症候群(非典型肺炎))とは何ですか?」
・ SARSは急性の呼吸器感染症で、香港を含む世界各地で多くの症例が報告されています。新しい媒体による、非典型的な肺炎です。 ・ 香港の保健衛生当局及び関連機関は、SARSの拡大を防止するため、世界保健機関(WHO)とも連携しつつ、共同で作業を進めています。 ・ SARSは、1メートル程度の近距離において、患者の呼吸器の飛沫又は呼吸器の分泌液との接触によって感染します。 ・ SARSの症状は、発熱(38度以上)、悪寒、咳、息切れ、頭痛、筋肉のこわばり、全身の倦怠感などを伴います。 ・ 呼吸疾患の症状がある方は、直ちに医師に相談するとともに、マスクを着用してください。 ・ 早期に診断された患者のほとんどは、回復の兆候を示しており、そのうちすでに退院した方もいます。
「どのような予防措置を講じたらよいのですか?」
(身の回りを清潔にしておくこと) ・ 咳やくしゃみをするときは、鼻や口をティッシュペーパーで覆い、すぐさま、そのティッシュペーパーを捨ててください。 ・ 液体石けんでこまめに手を洗う。 ・ 咳やくしゃみあるいは鼻をかんだ後はすぐに手を洗う。 ・ 目、口、鼻をさわる前には手を洗う。 ・ トイレに行った後は手を洗い、公共施設の設備に触れた後は、帰宅後手を洗い、使い捨て紙タオル又はハンド・ドライヤーで手を乾かす。 ・ タオルは他人が使ったものを使用しない。 ・ 食器は共用しない。 ・ 抵抗力を強める。バランスのとれた食事をとる。定期的に食事をし、十分に休養をとり、ストレスを少なくし、たばこは吸わない。 ・ 混雑した場所は避ける。 (家庭や職場を清潔にしておく) ・ 家庭や職場は、最低一日一回、防菌剤又は液体洗剤を使ってきれいにする。全般的な清掃は、薄めた液体洗剤(洗剤1:水99)を使い、清潔な水に浸したタオルで再度拭き取る。感染者が接触したと思われる箇所については、より濃い目の洗剤(洗剤1:水49)(注)を使い、清潔な水に浸したタオルで再度拭き取るか、または、清潔な水ですすいだのち、乾燥させる。 ・ 時々、窓を開けて、屋内の換気を行う。空調機のメンテナンスを良くし、フィルター部分は頻繁に洗浄する。 ・ トイレは清潔にする。液体石鹸、使い捨てタオル、ハンド・ドライヤーを備え付ける。
「家族、同僚、友人が感染した場合、どのように対処すればいいですか?」
・ SARS患者は入院しなければなりません。 ・ 同居者、感染者を看護した方は、10日間毎日指定された医療機関で、検査を受けなければなりません。 ・ 衛生署は、これらの医療検査におかれる方々に関する特別ガイドラインを公表する予定です。医療検査期間中は、仕事を休んで、自宅待機しなければなりません。また、真に必要がない限りは、自宅から外出もしてはいけません。外出しなければならない場合には、マスクを着用し、清潔な状態を保つ必要があります。 ・ 感染していない関係者(例:友人、同僚)が感染者と接触する場合には、別途提供される特定の情報とホットライン番号(での案内)に従ってください。これらの関係者で呼吸器疾患の兆候が現れた場合には、指定医療機関で診察を受けることをお勧めします。
【一般的なガイドライン】
(家庭において) ・ 住居を清潔に保ち、室内の換気を良くする。 ・ 外出から戻ったら、手をよく洗う。 ・ 呼吸器疾患の家族を看護した場合、 - もし体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を受ける。 - 処方された薬を使用する等、医師の指示に従う。 - 十分な休養をとる。 - 身の回りを常に清潔に保つ。 - 感染する機会を減らすためマスクを着用する。 (学校において) ・ 病気の子供は学校や保育園で預からない。 ・ 子供が学校で病気になった場合、 - 速やかに両親や保護者に連絡し、医師の診察を受けるようアドバイスする。 - 病気の子供を正常な子供から離し、呼吸器疾患や発熱の兆候がみられたら、マスクを着用させる。 - 呼吸器疾患の兆候が見られる子供と接触する際は、マスクを着用する。 ・ 学校は子供や職員の病欠記録を保存する。病欠者が増加した場合、 - 病欠の子供の両親(保護者)や職員と連絡を取り、病欠の理由を確認する。 - 類似の症状で多数の欠席者が生じた場合には、衛生署に通報する。 ・ 学校の設備・施設を清掃し、室内の良好な換気状態を維持する。 (職場において) ・ 呼吸器に疾病の症状がある場合には、すみやかに医師に相談し、病休をとる。 ・ もし職員がSARSと診断された場合には、管理者は、速やかに他の職員及び衛生署に通知する。 ・ 職場を清潔にし、室内の良好な換気状態を維持する。 (レストラン、映画館、市場等の公共スペースにおいて) ・ 呼吸器障害の兆候が見られた場合には、いかなる場合でもマスクを着用する。 ・ 食品の準備、取扱い(給仕)に関係する場合には、マスクを着用する。 ・ 液体石けんでこまめに手を洗う。 ・ 使用済みのティッシュペーパーは、ふた付きのゴミ箱の中に廃棄し、その後必ず手を洗う。 ・ つばを吐かない。 ・ トイレの施設は確実に清潔な状態を維持し、正常に作動することを確認する。液体石けん、及び使い捨ての紙タオル又はハンド・ドライヤーを備え付ける。 (マスクの着用) ・ マスクを適切に着用することにより、呼吸器の感染症を防ぐことができます。呼吸器に疾病の症状のある人、又は非典型肺炎患者であると確認された患者と緊密な接触をした人は、感染拡大の可能性を抑えるためにマスクを着用しなければなりません。確認された患者又は病院に患者を見舞う人もまた、マスクを着用しなければなりません。一般の方も、自らを保護するためにマスクを着用するのが望ましいでしょう。 ・ マスクの着用前には手を洗いましょう。マスク製造社の取扱説明書に従い、付属のひもやゴムひもを使用して、マスクが確実にぴったりと顔に密着するようにします。 ・ マスクの色つきの面が外側となるように着用し、鼻、口、及びあごを完全に覆うように着用します。漏れのないよう、マスクの中の金属製の棒を変形させて、鼻梁にしっかりと固定します。 ・ 外科手術用マスクは通常の環境で最低一日一回は取り替えましょう。使用済みのマスクはビニール袋に入れ、ビニール袋の口をきちんと閉め、ふた付きのゴミ箱に廃棄します。マスクがすり切れたり破損したりした場合にはすみやかに取り替えましょう。
より詳しい情報については、 2833 0111 衛生署の音声テープ健康情報ホットライン、又は 2961 8968 衛生署ホットライン(執務時間中)、又は 衛生署のウェブサイト www.info.gov.hk/dh をご覧ください。